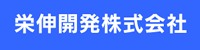食品リサイクル法について
改正食品リサイクル法が平成19年12月1日に施行されました。
●食品関連事業者に対する定期報告の義務化
食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者(食品廃棄物等多量発生事業者)
は、毎年度、主務大臣に、食品廃棄物等の発生量および食品循環資源の再生利用等の状況を
報告することが、義務付けられました。
毎年度、6月末日までに前年度の状況について、
電子申請または書面および電子媒体により報告します。
報告は平成20年度の状況を平成21年4月~6月に行います。
定期報告書の様式は下記のホームページでご覧いただけます。
みえエコくるセンターでは、食品残渣の自動計量システムを導入しており、食品廃棄物の発生量と食品リサイクル率を把握することができます。
●食品関連事業者ごとの再生利用等実施率の目標の改正
すべての食品関連事業者に、平等に規制をかけるということで、今回の改正で再生利用等の実施率は2通りの目標を設定しました。
(1)業務別再生利用等実施率目標(重量ベース)
平成24年度までに、業種別に下記の実施率目標を達成することを目標とします。
○食品製造業 85% ○食品小売業 45%
○食品卸売業 70% ○外食産業 40%
(2)食品関連事業者ごとの再生利用等実施率目標
食品関連事業者の再生利用等実施率が、毎年度、食品関連事業者ごとに設定された当年度の基準実施率を上回ること。
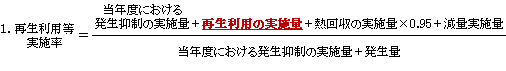
2.基準実施率=前年度の基準実施率+前年度基準実施率に応じた増加ポイント
(但し、平成19年度の基準実施率は、平成19年度再生利用等実施率(実績)とします。)
増加ポイント(A)
| 前年度の基準実施率区分 | 増加ポイント |
|---|---|
| 20%以上50%未満 | 2% |
| 50%以上80%未満 | 1% |
| 80%以上 | 維持向上 |
※平成19年度再生利用等実施率が20%未満の場合は、20%として基準率を計算します。
(例)A事業者
算出した平成19年度再生利用等実施率(実績)が45%の場合、
|
平成20年度 45%+2%=47% |
← | ◎この基準率が、A事業者の目標となります。 |
●フランチャイズチェーン事業者
約款に基づき廃棄物の処理に関して加盟店を指導出来る関係にある場合には、加盟店の食品廃棄物等の発生量を含めて食品廃棄物等多量発生事業者であるか判定することになります。該当した場合、本部は加盟店の再生利用等の実施状況も含めての定期報告となります。
●再生利用事業計画の認定制度(リサイクルループ)の見直し
今までの再生利用事業計画の認定制度は、食品関連事業者が飼料や肥料の製造業者と農林漁業者などと三者一体の取り組みを進め、大臣認定を受けるという制度でしたが、新しい制度では、食品関連事業者→リサイクル業者→農業従事者→食品関連事業者へとリサイクルループを完結させることが認定の要件となります。
認定を受けられれば、一般廃棄物の収集運搬許可について、通常は、各市町村から許可を得るものを特例と、認定計画の範囲内について市町村からの一般廃棄物収集運搬業の許可が不要になります。
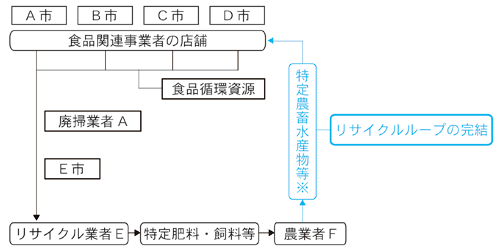
※特定農水産物等とは
・特定の肥料・飼料等の利用により生産された農畜水産物
・原材料として利用される農水産物のうち特定農畜水産物が重量割合で50%以上含まれる食品
(例えばミックスベジタブルに使われている野菜の50%以上が特定農水産物であること)
リサイクルで作られた堆肥を使って作られた農作物が食品関連事業者にどれだけ引き取られているかを算定する計算式
特定農畜水産物等の利用量=(A-B)×{(C÷D)×(E÷F)}×0.5
A:計画に基づき、農林漁業者等が生産する特定農畜水産物の量
B:Aのうち、農林漁業者等が既に計画外で販売を確保している量
C:特定肥料・飼料の製造に利用される食品循環資源の量
D:特定肥料・飼料の製造に利用される原材料の総量
E:特定農畜水産物の生産に使用する特定肥料・飼料等の量
F:特定農畜水産物の生産に使用する肥料・飼料等の総量
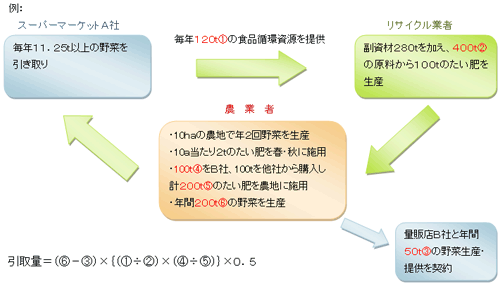
【用語解説】
- (1) 発生量:
- 当該年度中に発生した食品廃棄物等の量
【(3)+(4)+(5)+(6)+(7)】 - (2) 発生抑制量:
- 平成19年度発生原単位から当該年度発生原単位を減じた値に、当該年度の発生量と密接に関係を有する数値で乗じた量
- (3) 再生利用量:
- 当該年度中に再生利用過程に投入された食品循環資源の量
- (4) 熱回収:
- 当該年度中に熱回収に投入された食品循環資源の量
- (5) 減量量:
- 当該年度中に減量の効果として減少した食品廃棄物等の量
- (6) 再生利用等
以外の量: - 当該年度中に再生利用等以外の過程に投入された食品循環資源の量 以外の量
- (7) 処分量:
- 当該年度中に廃棄物として処分された食品廃棄物等の量
●登録再生利用事業者制度(食品リサイクル法資料より抜粋)
食品リサイクル法では、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用に取り組むときに、より実施しやすい
環境を整えるためにいくつかの制度を設けています。
登録再生利用事業者制度もその一つで、優良な
再生利用事業者を育成することを目的として、再生利用事業を的確に実施できる一定の要件を満たすものを登録する制度です
●登録の要件
・肥料化等の事業内容が、生活環境の保全上支障がないものであること
・施設の種類や規模が、事業を効率的に実施するに足りるものであること
(食品循環資源の処理能力5トン以上/日)
・事業実施に十分な経理的基礎があること
●登録された場合のメリット
食品関連事業者にとって
・優良な再生利用事業者の選択が容易になります。
再生利用事業者にとって
・登録されることにより、受託先の拡大等が期待できます。
・肥料取締法、飼料安全法の特例が受けられます。
製造、販売等の届け出を重ねて行うことは不要となります。
・廃棄物処理法の特例が受けられます。
荷卸し地における一般廃棄物の運搬にかかる業許可が不要になります。
(荷積み地における市町村からの業許可は必要)